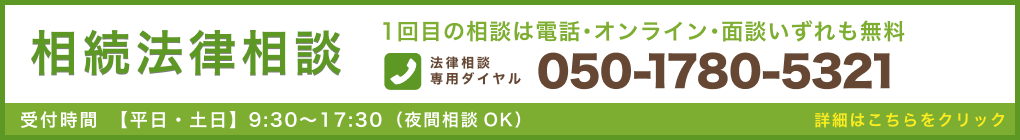- 4月
- 12
- Thu
亡くなった方に、相続人がいない場合・・・
人が亡くなったときに、相続が開始します。この場合、法定相続人となる資格を有する者がいらっしゃる場合には、その方が被相続人の財産を相続することになります。
また、相続人がいらっしゃらないときでも、被相続人の方が生前に遺言を作成していれば、その方が被相続人の財産を取得できます。
では、生前の遺言も存在せず、法定相続人がいない場合には、亡くなった被相続人の財産はどうなるでしょうか。
生前、被相続人の介護等の世話をしていたり、被相続人に資金面の援助をしていた方がいらっしゃるときに、被相続人の財産を取得することはできないでしょうか。
法律上、相続人のあることが明らかでないときは、被相続人の相続財産は、法人となります(民法951条)。これは、相続財産について、所有者がいない状態になることを防ぐためです。
この場合、利害関係人等の請求があったときに、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、被相続人の財産について、精算・管理を行います。
相続財産管理人は、その後も、相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所に対して、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨の公告をするように請求します。
そして、この一定の期間内(最低6ヶ月)において、相続人としての権利を主張するものが表れなかった場合には、本来の相続人及び受遺者はその権利を行使することができなくなります。
そして、この場合に、亡くなった方の財産は、どうなってしまうのでしょうか。財産はすべて国庫に帰属されてしまうのでしょうか。
ここで、法律では、家庭裁判所が相当と認めるときには、一定の範囲の人に、亡くなった方の財産の全部又は一部を与えることができるとされています。
この、一定の範囲の人とは、「特別縁故者」と言われます。
いかなる人が特別縁故者に該当するかについては、法律上「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者」などと定められていますが、これはあくまで、例示であり、最終的には裁判所の裁量にゆだねられています。
なお、特別縁故者の方の相続財産の分与の申立は、上記の公告期間の満了後、3ヶ月以内にする必要がありますので、ご注意ください。
もし、身寄りがいないような方のお世話をされていた方や、生前に金銭的な援助等をしていたことがあるような方で、自身が特別縁故者に該当するか疑問に思われた方は、一度弊所にご相談されることをお勧めいたします。
岡崎事務所 弁護士 安井 孝侑記
岡崎事務所 弁護士 安井 孝侑記