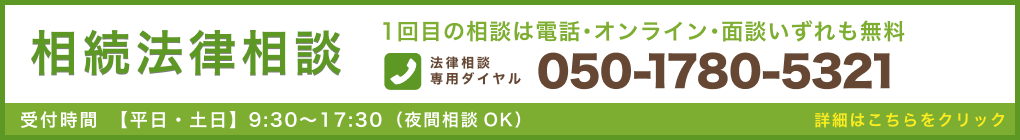- 5月
- 22
- Fri
相続の欠格
遺言書が無い場合には、相続人は亡くなった方との血縁関係があれば、相続人たる地位を取得し、法定相続分に従って遺産を相続するのが通常です。
もっとも、民法上これには幾つかの例外があり、相続の欠格はこの一つで、しかも重大な効果を持つものです。
相続の欠格とは、民法891条により、一定の事由がある者は、当然に相続人となることができないと定められているものです。
具体的には、
・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者、
・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
・詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
がこれにあたります。
「刑に処せられた者」、「殺害」、「詐欺又は強迫」(誤字ではありません)など、民法の規定にしてはなかなか物騒な言葉が並んでいますが、定められている内容の方向性としては大まかに言えば、相続に関係する人の生命を害する行為に関係し、または被相続人の相続に関する意向に違法な干渉をするような違法な行為を行う者が遺産を取得することを許さない、ということになるでしょうか。
条文に上げられている事柄は、いずれもそれ自体犯罪であるか、もしくは犯罪との関連性がある事柄であって、こうした事由に該当するケースはそれほど多くはありませんし、実行してしまう方は少ないでしょう。
もっとも、長年手厚く面倒を見てきた被相続人が自分に不利益な相続を残したことを知ってしまったような場合には、つい魔が差して、衝動的にこうした遺言書を握りつぶしてしまうなどの行為に走りかねない、ということもあるかもしれません。また、ご自身でなく、逆に他の相続人がこうした行為を行っていることが疑われるようなケースも当然ながらあると思います。
こうした短絡的な行動が招く結果は、相続人となれない、すなわち一切の遺産を相続できない、ということです。相続との関係だけでも重大な結果を招く行為であって一時の感情で行動するべきではありません。
相続の欠格については、その欠格事由の有無を裁判手続において証明する必要があり、こうした事態が疑われるような場合には、弁護士に依頼する必要性が高いと言えます。
万が一、こうしたトラブルが発生した場合には、是非一度ご相談下さい。
丸の内本部事務所 弁護士 勝又敬介
丸の内本部事務所 弁護士 勝又 敬介