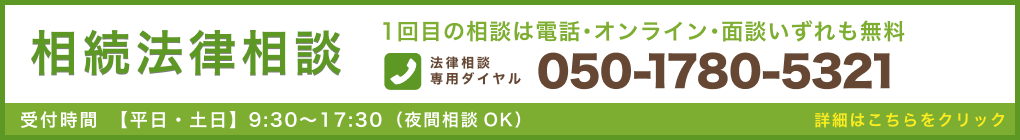津島事務所で勤務しております,深尾至と申します。私は今年の4月まで名古屋丸の内本部事務所で勤務していたのですが,津島では,名古屋よりも相続についてのご相談を受けることが多いと感じています。 被相続人の生前,その介護等に尽力された方の中には,「私は,被相続人のためにこれだけのことを行ったのだから,遺産分割の際にこれを考慮して欲しい。」とお考えの方もおられるかと思います。 相続が開始すると,共同相続人は,原則として,民法で定められた相続分(法定相続分)に応じて被相続人の権利義務を承継します。被相続人の子の法定相続分は等しいものとされていますから,被相続人の介護等にどれだけ尽力しても他の兄弟と法定相続分は同じことになります。 もっとも,民法には,この法定相続分を修正する制度が定められており,その1つが寄与分です。 寄与分とは,共同相続人中に,被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした人がいるときに,その寄与に相当する額を法定相続分に上乗せすることを認める制度です(民法904条の2)。 例えば,遺産が1500万円の現金のみであり,相続人が被相続人の子3人であったとします。この場合に,長男に300万円の寄与分が認められると,1500万円から300万円を引いた1200万円を相続財産として計算します。そして,長男はその3分の1である400万円に寄与分300万円を足した700万円を相続し,他の相続人は400万円ずつ相続します。 寄与分は,上記のとおり,「特別の寄与」をした人に認められますが,どのような行為が「特別な寄与」と評価されるのでしょうか。 一般的には,ある行為が,被相続人との身分関係において通常期待される程度を超える貢献であると言える場合,その行為は「特別の寄与」と評価され,その考慮要素としては,①通常の家族関係で一般的に期待される程度を超えること(行為の特別性),②報酬などを受け取っていないこと(無償性),③ある程度の長期間続けたこと(継続性),④片手間で行っていないこと(専従性)等の点が挙げられます。 一般的には上記のとおりですが,寄与分が認められるかどうかは,まさにケースバイケースです。冒頭のようにお考えの方は,寄与分が認められ得るケースであるのか,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
津島事務所 弁護士 深尾至
津島事務所 弁護士 深尾 至
遺言書については,いろいろな種類の遺言書(例えば,自筆証書遺言,公正証書遺言等)がありますが,実務上よく問題となるのは,自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)です。 遺言書は自分でも書くことができ,費用もかからず,お得であるようにも思えます。 しかし,民法上,全文,日付,氏名を自署し,印を押さなければならないとしてあり,この要件を満たさなければ,無効となります。 このような要件だったら,簡単じゃないかと思ったりするかもしれません。たとえば,遺言書のどこにも日付がなければ無効になるのは当然です。ですが,封筒にのみ日付がある場合はどうか,封筒が開封されていた場合はどうか,誤字はどうなるか等,微妙で難しい問題も多々あります。 そして,このような形式的な面から,無効とされる遺言書も多々あります。 以上のように,自筆証書遺言で遺言を行うことは,相当程度リスクがあります。遺言が無効となると,遺言者の意思を実現することができないことになってしまい,遺言者にとってはあまりに酷です。 したがって,多少の時間とお金をかけてでも公正証書遺言にする,ないしは,弁護士に相談して遺言書を作成するなどの,確実な方法を取った方がよいです。 もし,遺言書のことでお困りでしたら,お一人で悩まず,お気軽に相談してください。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 北澤嘉章
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 北澤 嘉章
被相続人が亡くなると,相続が開始します。遺言書がある場合には,遺言書に従って相続がなされますが,遺言書がない場合には,どのように相続がされるのでしょうか。民法には,原則として誰が相続人となるのか(相続人の範囲),どんな割合で相続するのか(相続分)等について定めがあります。 相続人の範囲については,分籍や,長期間音信不通等の様々な事情で,親族の間でもよくわからなくなっていることがあります。遺産分割協議には必ず全ての相続人が参加しなければならず,一部の相続人が参加せずにした遺産分割協議は無効になってしまいますので注意してください。参加した相続人の間でやっと話がまとまったと思っても,他にも相続人がいることがわかれば水の泡になってしまいます。 そこで、遺産分割協議をする前には,被相続人の出生から死亡までの戸籍や,各相続人の戸籍を取得するなどして誰が相続人なのかを調査することをおすすめします。なお,相続人であれば,被相続人の戸籍の取得はできますが,被相続人の戸籍から分籍した他の相続人の戸籍を取得することはできないため,これらの戸籍取得も含めた調査という点で,私たち弁護士はお役に立つことができるのではないでしょうか。 そして,いざ相続人の範囲が決まった!となると,次は具体的にどの遺産を誰が取得するのかを協議します。遺産分割の局面では,様々な感情が交錯しやすく,「本当はあの不動産が欲しいけれど,他の人に言いにくい…。」などということもよく見られます。ほとんど面識のない親族に対して,率直な意見を言いにくいこともあるでしょう。弁護士は,依頼者の代理人として,他の全ての相続人との連絡窓口となり交渉していくため,遺産に関し直接他の相続人と話さなければならないという心理的負担を軽減することができます。 私は春日井事務所で勤務しておりますが,弊所は,本部の名古屋丸の内をはじめ,小牧,津島,名古屋新瑞橋,日進赤池,名古屋藤が丘,高蔵寺にも支所がございますので,お近くの事務所までお気軽にご相談下さい。
春日井事務所 弁護士 友近歩美
春日井事務所 弁護士 友近 歩美
遺言によって,財産の相続について亡くなる方の意向を反映することができます。もっとも,亡くなった方が「全財産を愛人に譲る」旨の遺言を作成していた場合,亡くなった方の財産に依存して生活していたご家族が生活できなくなるという事態も生じかねません。民法では,このようなご家族の不利益を考慮し,「遺留分」について規定しています。遺留分とは,一定の相続人が最低限相続できる財産の一定の割合のことをいいます。遺留分権利者は,遺留分を侵害する内容の遺言等により財産を取得した人に,遺留分減殺請求をすることができます。遺留分権利者は,夫や妻といった配偶者,子,父や母といった直系尊属です。ご兄弟には,遺留分は認められません。遺留分減殺請求をできる期間は,遺留分権利者が相続の開始を知り,被相続人の財産の贈与又は遺贈があった事実を知ったことに加えて,その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年,あるいは,それを知らなくても相続開始の時から10年です。遺留分の割合や遺留分減殺の基礎となる財産の計算は複雑で分かりづらいものです。もし,遺留分でお困りでしたら,相続に強い愛知の弁護士が多数在籍する弊所へご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 田村 祐希子
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 田村 祐希子
1 はじめに最近,遺言をされる方が増えているようです。遺言には,①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言という3つの方式がありますが,この内,①自筆証書遺言について,最近出た2つの新しい最高裁判決を紹介します。一つは,平成27年11月20日の判決であり,もう一つは,平成28年6月3日の判決です。自筆証書遺言というのは,遺言書の全文が遺言者の自筆で記述されている遺言で,遺言者が,日付と氏名を自分で書いた上,押印することが必要な遺言です。 2 平成27年11月20日最高裁判決平成27年11月20日の最高裁判決で問題となったのは,遺言者が遺言書に赤い斜線を引いたことについて,遺言が無効となるかどうか,です。遺言は,遺言者が故意に遺言書を破棄した場合には撤回されたものと見なされ(民法第1024条),効力が失われます。そこで,遺言書全体に赤い斜線を引く行為が破棄に当たるか,が問題となりました。第1審の広島地方裁判所,第2審の広島高等裁判所は,元の文字が判読できる程度の斜線では,遺言の効力は失われないとして,遺言を有効と判断していました。これに対し,最高裁判所は,遺言は故意に破棄されたものであり無効であると判断しました。 3 平成28年6月3日最高裁判決平成28年6月3日の最高裁判決で問題となったのは,遺言者が押印の代わりに花押(署名の代わりに使用される記号・符号)をしていた場合に,押印の要件を満たすかどうか,です。原審の福岡高等裁判所は,花押は,文書の作成の真正を担保する役割を担い,印章としての役割も認められており,花押を用いることによって遺言者の同一性及び真意の確保が妨げられるとはいえない,として,遺言として有効であるとの判断をしました。これに対し,最高裁判所は,我が国では,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行や法意識があるとはいえないとして,押印の要件を満たさないので,遺言として無効であるとの判断をしました。 4 判決の理解と遺言作成に関する注意点遺言は,遺言者の最後の意思の表れであり,なるべくその意思を重視する必要がある反面で,遺言が効力を生じるときには,遺言者が既にこの世にいないため,本人に真意を確かめる術がないため,形式を重視して本人の意思を探らざるを得ないということがあります。上記の2つの判決は,そのような緊張関係にある2つの要請の中で,いずれも,最高裁判所と高等裁判所の判断が異なった事案です。また,両判決の判断は,いずれも遺言の効力を否定したものでありながら,その判断の方向性は異なっています。平成27年11月20日最高裁判決は,一義的でない斜線を引くという行為について遺言者の意思を忖度して遺言の撤回を認め,他方,平成28年6月3日最高裁判決は,方式の厳格性を重視して遺言者の真意を推測すること自体を避けて遺言を無効としました。この問題がいかに難しく,予測困難であるかが分かります。遺言を作るに当たって,公正証書遺言と比較して自筆で自由に作成できる自筆証書遺言ですが,方式が厳格であり,安易に作成すると,法的に有効なものとならないリスクもあります。遺言者は,その意思を守ってもらうためには,きちんとした方式を守らなければいけません。したがって,遺言を作ると決められたときには,専門家である弁護士に,一度,ご相談されることを強くお勧め致します。弁護士法人愛知総合法律事務所では,遺言に関する相談も,初回無料です。是非,お気軽にご相談を頂ければ幸いです。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 檀浦 康仁
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 檀浦 康仁